ここでは、【数学B】「数列」でよく利用する公式(基礎知識)や例題を一覧にしてまとめています。
1.等差数列
初項\(a\), 公差\(d\) の等差数列\(\{a_n\}\)の一般項は
\(\color{red}{a_n = a + (n – 1)d}\)
例題
初項\(2\), 公差\(3\) の等差数列\(\{a_n\}\)の一般項を求めよ。
解答
\(a_n = 2 + (n – 1) \cdot 3\)
\(= 3n – 1\)
数列\(a, b, c\)が等差数列 ⇔ \(\color{red}{2b = a + c}\)
例題
数列\(a, 2, 5\)が等差数列であるとき,\(a\) の値を求めよ。
解答
等差数列であるとき,\(2 \cdot 2 = a + 5\) であるから
\(a = – 1\)
① 初項\(a\), 第\(n\)項が\(l\)の等差数列の和\(S_n\)
\(\color{red}{S_n = \displaystyle\frac{1}{2}n(a + l)}\)
② 初項\(a\), 公差\(d\)の等差数列の和\(S_n\)
\(\color{red}{S_n = \displaystyle\frac{1}{2}n\{2a + (n – 1)d\}}\)
※①式において、\(l = a + (n – 1)d\)とすることで導くことができる
③ 自然数\(1, 2, 3, \cdots, n\)の和\(S_n\)
\(\color{red}{S_n = \displaystyle\frac{1}{2}n(n + 1)}\)
※①式において、\(a=1, l = n\) とすることで導くことができる
例題
初項\(2\), 第\(20\)項が\(40\)の等差数列の初項から第\(20\)項までの和\(S_{20}\)を求めよ。
解答
\(S_{20} = \displaystyle\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (2 + 40)\)
\(= 420\)
2.等比数列
初項\(a\), 公比\(r\) の等比数列\(\{a_n\}\)の一般項は
\(\color{red}{a_n = a r^{n – 1}}\)
例題
初項\(2\), 公比\(3\) の等比数列\(\{a_n\}\)の一般項を求めよ。
解答
\(a_n = 2\cdot3^{n – 1}\)
数列\(a, b, c\)が等比数列 ⇔ \(\color{red}{b^2 = ac}\)
※ただし、(\(a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0\))
例題
数列\(a, 6, 18\)が等比数列であるとき,\(a\) の値を求めよ。
解答
数列\(a, 6, 18\)が等比数列より,\(6^2 = 18a\)
\(a = 2\)
初項\(a\), 公比\(r\) の等比数列\(\{a_n\}\)の初項から第\(n\) 項までの和\(S_n\)は
① \( r \neq 1\) のとき
\(\color{red}{S_n = \displaystyle\frac{a(1 – r^n)}{1 – r} = \displaystyle\frac{a(r^n – 1)}{r – 1}}\)
② \(r = 1\) のとき
\(\color{red}{S_n = na}\)
例題
初項\(3\), 公比\(5\) の等比数列\(\{a_n\}\)の初項から第\(n\) 項までの和\(S_n\) を求めよ。
解答
\(S_n = \displaystyle\frac{3(5^n – 1)}{5 – 1}\)
\(= \displaystyle\frac{3(5^n – 1)}{4}\)
3.いろいろな数列の和
\(\displaystyle\sum_{k = 1}^n a_k =a_1 + a_2 + a_3 + \cdots\cdots + a_n\)
① \(\color{red}{\displaystyle\sum_{k = 1}^n c = nc}\)
※特に, \(\displaystyle\sum_{k = 1}^n 1 = n\)
② \(\color{red}{\displaystyle\sum_{k = 1}^n k = \displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1)}\)
③ \(\color{red}{\displaystyle\sum_{k = 1}^n k^2 = \displaystyle\frac{1}{6} n (n + 1)(2n + 1)}\)
④ \(\color{red}{\displaystyle\sum_{k = 1}^n k^3 = \left\{\displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1) \right\}^2} \)
例題
\(\displaystyle\sum_{k = 1}^5 k\) を求めよ。
解答
\(\displaystyle\sum_{k = 1}^5 k= \displaystyle\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (5 + 1) = 15\)
① \(\displaystyle\sum_{k = 1}^n (a_k + b_k) = \displaystyle\sum_{k = 1}^n a_k + \displaystyle\sum_{k = 1}^n b_k\)
② \(\displaystyle\sum_{k = 1}^n pa_k = p\displaystyle\sum_{k = 1}^n a_k\)
※\(p\) は \(k\) に無関係な定数
例題
\(\displaystyle\sum_{k = 1}^5 (2k^3 + k)\) を求めよ。
解答
\(\displaystyle\sum_{k = 1}^5 (2k^3 + k)\)
\(= 2\left\{\displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1) \right\}^2 + \displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1)\)
\(= \displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1)\{2 \cdot \displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1) +1\}\)
\(= \displaystyle\frac{1}{2} n (n + 1) (n^2 + n + 1)\)
4.階差数列
数列 \(\{a_n\}\) の階差数列を \(\{b_n\}\) とすると
※\(b_n = a_{n + 1} – a_n (n = 1, 2, 3, \cdots\cdots)\)
\(n \geq 2\) のとき \(\color{red}{a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k = 1}^{n – 1} b_k}\)
例題
\(2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, \cdots\cdots\) である数列\(\{a_n\}\) の一般項を求めよ。
解答
階差数列 \(\{b_n\} : 3, 5, 7, 11, 13, \cdots\cdots\) であるから初項\(3\), 公差 \(2\) の等差数列より、
\(b_n = 3 + 2(n – 1) = 2n + 1\)
したがって,
\(n \geq 2\) のとき
\(a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k = 1}^{n – 1} (2k +1)\)
\(= 2 + 2 \cdot \displaystyle\frac{1}{2}n(n – 1) + (n – 1)\)
\(= n^2 + 1\)
また、\(n = 1\) のとき
\(a_1 = 1^2 + 1 = 2\)
であるから、すべての自然数\(n\) について
\(a_n = n^2 + 1\)
5.数列の和と一般項
数列 \(\{a_n\}\) の初項から第 \(n\) 項までの和を \(S_n\) とすると
① \(a_1 = S_1\)
② \(n \geq 2\) のとき \(\color{red}{a_n = S_n – S_{n – 1}}\)
例題
初項から第 \(n\) 項までの和 \(S_n = n^2 + n\) である数列 \(\{a_n\}\) の一般項を求めよ。
解答
\(n \geq 2\) のとき
\(a_n = S_n – S_{n – 1} = (n^2 + n) – \{(n – 1)^2 + (n – 1)\}\)
\(= (n^2 + n) – (n^2 – 2n +1) + (n – 1)\)
\(= 4n – 2\)
また,\(n = 1\) のとき
\(a_1 = S_1 = 2\) であるから
\(a_n = 4n – 2\)
6.複雑なΣの計算のテクニック
以下のテクニックを利用することで、複雑な\(\sum\) の値を計算することができる。
\(\displaystyle\frac{px + q}{(x + a)(x + b)} = \displaystyle\frac{A}{x + a} + \displaystyle\frac{B}{x + b}\)
例題
\(\displaystyle\frac{1}{(x + 1)(x + 2)}\) を部分分数分解せよ。
解答
\(\displaystyle\frac{1}{(x + 1)(x + 2)}\)
\(= \displaystyle\frac{1}{x + 1} – \displaystyle\frac{1}{x + 2}\)
(等差数列)×(等比数列)の数列の和\(S\) は、\(S – rS\) を計算することで求めることができる。
※\(r\) は等比数列の公比
例題
\(S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n\) を計算せよ。
解答
\(\begin{cases}\quad S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n\\ -) 2S_n =\quad \quad \, \, 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \cdots + (n – 1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n + 1}\end{cases}\)
\(-S_n = 1 \cdot 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n – n \cdot 2^{n + 1}\)
\(-S_n = 1 \cdot 2 + \displaystyle\frac{2^{n + 1} – 2^2}{2 – 1}- n \cdot 2^{n + 1}\)
\(-S_n = 2 + (2^{n + 1} – 4) – n \cdot 2^{n + 1}\)
\(S_n = – 2^{n + 1} + n \cdot 2^{n + 1} + 2\)
7.漸化式と一般項
① \(a_{n + 1} = a_n + d\) ⇒ 公差 \(\color{red}{d}\) の等差数列
② \(a_{n + 1} = ra_n\) ⇒ 公比 \(\color{red}{r}\) の等比数列
③ \(a_{n + 1} = a_n + (n の式) \) ⇒ 階差数列を利用
④ \(a_{n + 1} = pa_n + q\)
⇒ \(\color{red}{a_{n+1} – c = p(a_n – c)}\)に変形
⑤ \(a_{n + 1} = ca_n + c^{n+2}\) (\(c\)は定数)
⇒ 両辺を\(\color{red}{c^{n + 1}}\) で割る
⑥ \(a_{n + 1} = \displaystyle\frac{a_n}{pa_n + q}\) (\(p, q\)は定数)
⇒ 両辺の逆数をとる
例題
次の漸化式を満たす数列\(\{a_n\}\) の一般項を求めよ。
(1) \(a_{n + 1} = a_n + 3 , a_1 = 2\)
(2) \(a_{n + 1} = 5a_n, a_1 = 3\)
解答
(1)数列\(\{a_n\}\)は初項\(2\), 公差\(3\) の等差数列より
\(a_n = 2 + 3(n – 1) = 3n – 1\)
(2)数列\(\{a_n\}\)は初項\(3\), 公比\(5\) の等比数列より
\(a_n = 3 \cdot 5^{n-1}\)
\(pa_{n+2} + qa_{n+1} +ra_n = 0\)
⇒ \(\color{red}{a_{n+2} – \alpha a_{n+1} = \beta (a_{n+1} – \alpha a_n )}\) に変形
\(n\) 回目と \((n + 1)\) 回目に注目して,確率\(p_n\) と\(p_{n+1}\) の漸化式を作る。
8.数学的帰納法
自然数 \(n\) に関する事柄 \(P\) が,すべての自然数\(n\) について成り立つことを証明するには, 次の [1] と [2]を示せばよい。
[1] \(n = 1\) のとき \(P\) が成り立つ。
[2] \(n = k\) のとき \(P\) が成り立つと仮定すると,\(n = k + 1\) のときにも\(P\) が成り立つ。
例題
\(n\) が自然数のとき,数学的帰納法によって次の等式を証明せよ。
\(1 + 2 + 3 + \cdots + (n – 1) + n = \displaystyle\frac{1}{2}n(n + 1) \cdots ①\)
解答
[1] \(n = 1\) のとき
\((左辺) = 1\)
\((右辺) = \displaystyle\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1 + 1) = 1\)
よって、\(n = 1\) のとき①は成り立つ
[2] \(n = k\) のとき①が成り立つと仮定する
すなわち
\(1 + 2 + 3 + \cdots + (k – 1) + k = \displaystyle\frac{1}{2}k(k + 1)\)
であるとする
\(1 + 2 + 3 + \cdots + (k – 1) + k + (k + 1)\)
\(= \displaystyle\frac{1}{2}k(k + 1) + (k + 1)\)
\(= \displaystyle\frac{1}{2}(k + 1)(k + 2)\)
\(= \displaystyle\frac{1}{2}(k + 1)\{(k + 1) + 1\}\)
よって、\(k = n + 1\) のときも①は成り立つ
[1], [2] からすべての自然数\(n\) について①が成り立つ

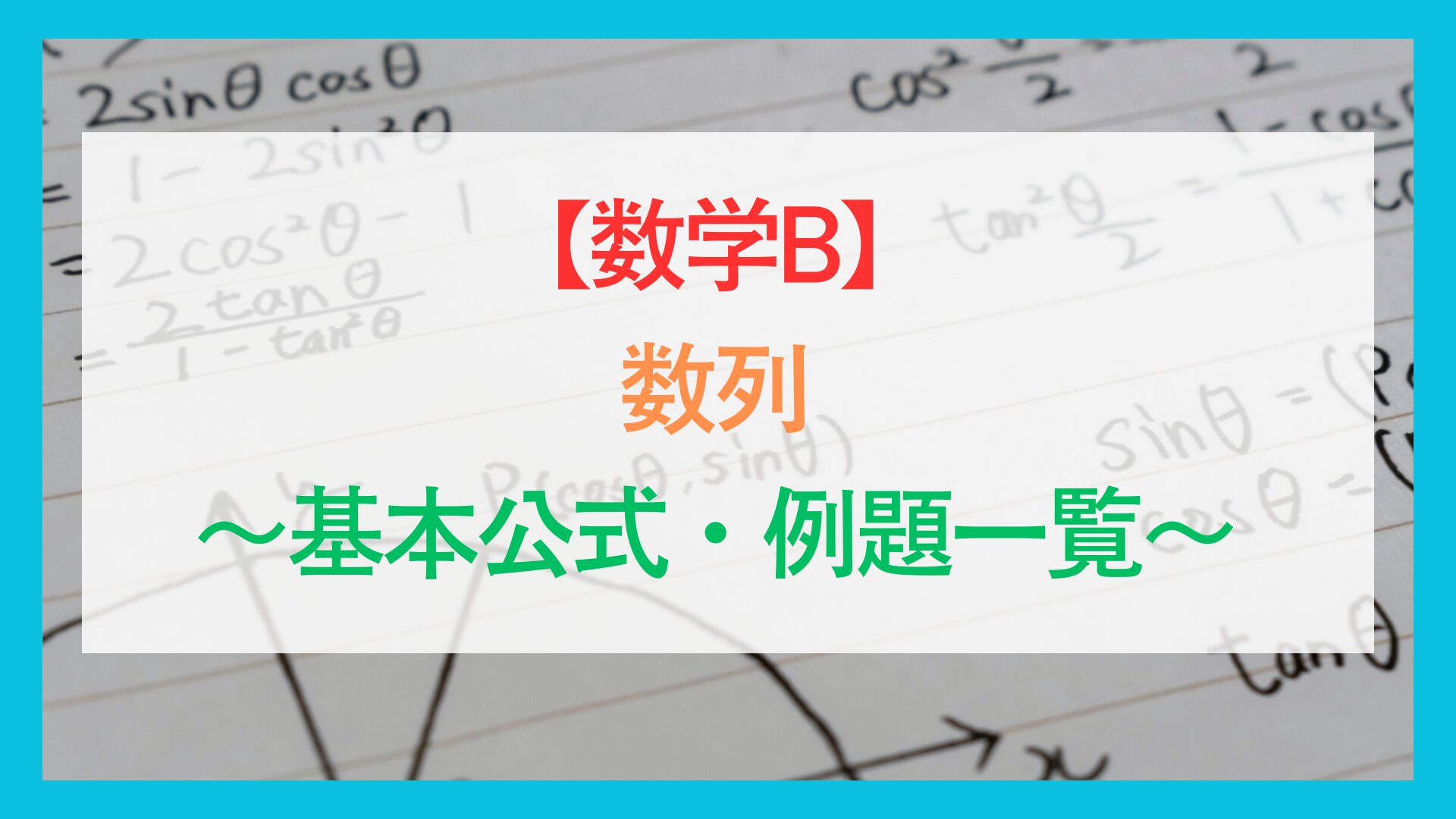

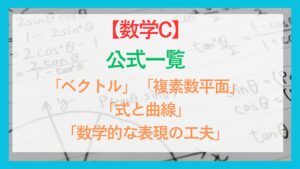
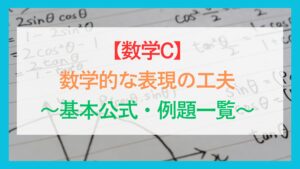
コメント